バイオエピステモロジーの観点からすと、J・ユクスキュル(Jakob J. B. von Uexküll:1864~1944)は、本格的に取りあげるべき重要人物である。なかでも『理論生物学 Theoretische Bioloie』(1928)は、その認識論的基本が、バイオエピステモロジーの問題設定と、よく適合する理論的な作品である。以下は、その初版序文と序論の和訳である。
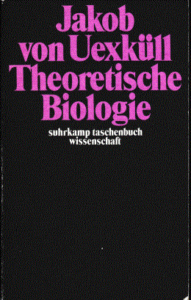
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
初版前書き(Vorwort zur ersten Auflage)
自然科学は、学説と研究の二つから成る。学説は、自然に対して明確な見解を述べるものである。これらはそれ自身が自然という権威のうえに、学説の形で展開する。
だが、と言うのは、間違いである。自然は学説を提示するのではなく、たんに現象のなかでの変化を示すだけである。これらの変化は、われわれが立てた問いへの回答として利用できるだけである。自然に対する科学の立場についての正しい理解を得るには、学説すべてを問いの形に変換し、科学者がそれへの回答に用いている証拠を、自然現象の変化の弁明に充てなければならない。
研究とは、問いの形の仮説(Hypothese)を立てる以上のものではなく、そこでの回答(These)は、すでに明確なものである。解答と学説の定立についての最終的な認識は、研究者が自然のなかに変化をじゅうぶんな数を観測すれば、その仮説の意味は肯定もしくは否定されることになる。学説が依拠する権威は、自然のなかにあるのではなく、自身が立てた問いに答える研究者の側にある。
われわれはただ、学説の形で自然科学の最終的な成果を受け容れるだけであり、そこからさまざまな論理規則を動員して思弁を試みることになるのだが、少なくとも日々、自然と直接やりとりをしている農夫や庭師と比べると、自然については何も知らない。
しかし、農夫や庭師自身は、問いを立てる技能を持っていないから、自然科学者ではない。
この問いを立てる技能は、自然科学のすべての認識への入り口を形成する。ただし生物学の場合、それは、すべての学説の中心にある固有の困難と結びついている。
私はこの本で、生物学的学説の本質について、決着をつけられる問題はないことに疑問はないという形で、生物学について考察を進めようと思う。
自然はすべて確実だが、科学はすべて問題含みである(In der Natur ist alles gewiß, in der Wissenschaft ist alles problematisch)。科学は、自然という建物に対する足場(Gerüst)を築いたときはじめて、その目的を果たしたことになる。科学の目的は、探求者が全体の展望を見失う心配をすることなく、どこにでも接近可能な確かな支えを構築することにある。だからなにを置いても、足場自体は自然に属すのではなく、むしろこれと敵対するような、しかしそれでいて決して矛盾が生じないような構造の足場を、できる限り確実に構築しなくてはならない。
このことは、足場は、常時更新される必要があることを意味する。そしてこの本では、この足場の更新を試みる。
こうする理由は次のような事情からである。これまでわれわれは、生物的自然のなかにある計画性(Planmäßichkeit)を扱うすべての問題において、この計画性をあっさり否認してきた。今後、このような姿勢はとらない。多数の動物が、最初は独特な物質の混合から発生してきたとわれわれは考える。すると、この問いに対する探求から、すべての動物は受精卵から発生し、その細胞からすべての細胞が生まれる、という認識に達する。
「すべての細胞は細胞から」という学説法則である。ここからわれわれは、すべての生きた細胞は、原始スープから生まれたに違いないという仮説に至る。このような手法で、われわれは、自然要因から計画性を排除しようとしてきた。
原始の昔に存在したという原始スープは、単なる想像であり、実験によって肯定も否定もされない。だからわれわれは、生物的自然には自律的な計画性という要因が存在するのかという問いに対して、自然のなかの計画性という見方の有効性を見定め、それに対しての否定的な主張と、肯定する物的証拠を対比させるためにも、他の手法について考え出さなければならない。
近年、その物的証拠は蓄積しており、この問題は決着がついたとみてよい。「細胞は細胞から」という原則には、「計画性は計画性から」という原則を付け加えるべきである。こうして生物学には、新しい足場が必要になる。これまで借りていた物理学と化学という足場では、まったく不十分である。なぜなら、物理と化学は、計画性を自然要因と見なさないから、生物学は、計画性を生命の基本と見なす学説に応じた足場を築く必要がある。
この足場構築の難しさは、そのための概念が手元にほとんどなく、新しく問題定立を行いながら作っていかなくてはならないところにある。
教科書は、一定の図式に従って一定の順序で事実を述べるものだが、本書の場合、これは適切ではない。読者は、この足場全体を理解するためには、一定の順序で読み通さなければならない。そうすれば読者は、一定の見解にたつ足場が誤りであるか、改善が必要であるか、あるいは足場全体を拒否すべきか、最終的な判断に至るはずである。
序論(Einleitung)
現代の生物学は、一定の学問領域を占めるだけではなく、物理・化学の基礎概念からは決して導出できない、固有の理論的基盤をもっていることを主張する。
理論生物学の必要性が意識され始めたのは、比較的最近のことである。動物学や植物学という生物学の専門分野が、記載に自らを限定しているのだから、事実の大量の素材を見通しの良い配列に並べるための特別の努力が必要なのだが、理論的基盤を求める特別の努力が必要だとは思われていない。
形態の記載という行為からは、生命の過程の維持については、物理と化学の方法で基本的に十分であることになる。それゆえ、生命という存在を物理・化学的な機械と見なすことに行きつく。
このような方向の考え方は、主観がうけとる現象を客観的過程として関連づける試みでしかなく、いったん否認されるべきである。生命の要素に対してわれわれが出会うのは、物理・化学的な法則には決して従属しないものである。だが、この物理・化学には、時間の経過とともに、「将来、この考えは実現されるかもしれない」という希望が吹き込まれる。こうして生理学的心理学は、「心理学は、生理学的原理によって処理されることになる」と言うに至るだろう。心理生理学にとり組む、ある有能な物理学者が、この方向性を決定的にした。ヘルムホルツは、われわれの周囲のものすべてを首尾一貫した様式で、感覚の性質にまで分解してしまう。
この感覚の性質は、われわれが直感する最終要素で、独立した単位である。分離不能で不変、変化するのはその強度だけである。たとえば、赤と黄色の中間にあるオレンジ色への移行は、この二つの質の色が同時に作用するときにのみ現れる。
こうしてヘルムホルツは、感覚の性質を外部の現象の記号とみなし、これだけで説明をする。現象を並行する感覚性質に引き渡してしまうのであり、外部の現象は永久に知ることはできない。結局は、「信じて行動せよ」という有名な教訓をもって、実際には生理学的心理学の破綻を明らかにする。
もし、永遠の自然法則が、われわれの認識から切り離されるのだとすると、われわれの心理がその影響下にあるという理由は、まったく引き出せなくなる。
ヘルムホルツがわれわれに求めるのは、われわれからは独立した自然法則が存在するとう仰である。この要請は受け容れられるかもしれない。平均的な思想家にとっていまや、力と物質に信が置けないとすると、これは妥当な考えに思えてくる。
これまで、物理法則は仮説以外の何ものでもなかった。だがこうなると、それは、信仰教義としての権威を獲得し、小さな神のように熱心に布教されるものとなる。
だがそうなると、研究はまったく不満足なまま放置され、信仰教義の上にすべてが構築されるとなると、教会の教説(Dogmen)以上のものではなくなってしまう。ヘルムホルツが感覚性質を現実の現象の主観的な記号とみなす以上、そういうことになる。
この見方は魅力的ではあるが、必須の仮説では絶対にない。ヘルムホルツ自身が示すように、われわれの周囲にある対象は、感覚性質のうえに築かれる。そして、他の人間はこれらの感覚性質をもって対象を構築する。これらは、主観が使用する記号もしくは指標以上のものではない。つまり、独立した現象について何も主張していない。
ヘルムホルツは、すべての対象はそれぞれの主観には別のものに見えることを認める。同時に彼は、現象の背後にある実在を求めようとし、これまでにいろいろ試みてきた。ただし先駆者たちとは違って、現象の背後に世界精神ではなく、物理学的な世界法則を想定する。これは好みの問題である。
ヘルムホルツはつねに徹底した物理学者であり、その抜きん出た才能に導かれて、唯物論(Materialismus)に立つことになる。ただし、それは意に反して、物理学の威光を失わせる、彼が決して近づくことのなかった道である。
主観を捨象することで、現象世界の背後の実在を探り当てようとする試みはすべて、世界を、それぞれの現象世界に委ねようとするものであり、そこから何も成果は出てこない。というのも、現象世界を組み立てる際、決定的な役割を果たすのが主観であり、現象世界の側に世界などないからである。
実在はすべて主観的現象である(Alle Wirklichkeit ist subjective Erscheinung)。この偉大な認識は、生物学においても該当する。主観からは独立した因果論によって世界を探求することは、完全に無益である。なぜなら対象の構築がまったく主観に負っているからである。
主観が構築する対象が現象である、という認識は、確かな伝統的な基礎をもっている。それはカントによって、すべての自然科学の体系の上に比類ない形で構築された。カントは、対象に対して人間の主観を対峙させ、基本原理を見つけ出した。これを受けて、われわれは精神によって対象を構築することになる。
